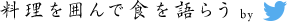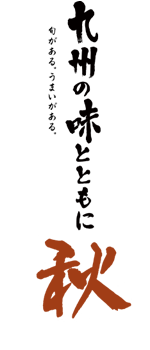

さつまいもと名水から生まれる
ほのかな甘味を持つ麺料理
一見するとそばのようだが、ツユの中にある麺は、そばのように長くはない…島原に伝わる『六兵衛』は、深江村(現在は南島原市深江町)の六兵衛という人が考案したと言われている郷土料理。六兵衛はかつて島原に飢饉が起きた時、保存食であったさつまいもの粉を美味しく食べられるようにと、この麺料理を考えだしたと伝えられている。
さつまいもを干して乾燥させ挽いた粉に、お湯やつなぎの山芋を入れてよくこねる。それをまるめた生地を、穴の開いた金属がはめこまれた『六兵衛おろし』や『六兵衛突き』と呼ばれる器具にのせ、押し出すことで麺をつくる。
麺はゆでるか蒸すかして火を通した後、ツユと合わせて丼に盛り、ネギやカマボコなどをのせてできあがりだ。
麺とツユをれんげですくい口の中へ。太くて短い麺は、表面はツルリ、中はもっちりとしていてさつまいものほのかな甘味を持つ。麺が甘味をもつため、通常のうどんやそばよりも、ツユをやや濃い味わいにしていることも特徴だ。添えられる柚子こしょうを加えても美味しい。
豊富な湧水で知られる島原。やわらかなツユの味も美味しい水があればこそ。『六兵衛』のやさしい味わいには、先人たちの知恵と自然の恵みが詰まっているのだ。
1792年、島原市に近い眉山(まゆやま)が崩壊し、津波も巻き起こり沿岸一帯には大変な被害が出た。(対岸の熊本にも被害が出たため、『島原大変肥後迷惑』として文献に残っている)。農地も荒れ米も麦も収穫できず飢饉に見舞われ、人々はやせた土地でも育つさつまいもを主食とするようになった。この時、深江村(現在は南島原市深江町)の六兵衛という人が保存食であったさつまいもの粉を美味しく食べるために考案したのが、『六兵衛』の始まりと言われている。
南島原市のイメージキャラクターはユーモラスな『六兵衛どん』。市内数カ所に『六兵衛どん』像が設置されている。

『六兵衛』の麺づくりを営んでいる『よしだや』の店主・吉田宗弘さんにお話をうかがった。
●吉田さんの麺づくり
「今、うちでつくっているのは、私の母親も昔から作っていたさつまいもの粉と山芋でつくる昔ながらのもの。小学校の給食にも出しているんですよ。材料のさつまいもは100%地元のもの。山芋は時期的に青森産のものを使っている時もあります。以前は粉を仕入れていたのですが、その方が製粉をやめてしまわれたので、今は農家から干したさつまいもを仕入れ、うちで製粉しています。農家の方々もご高齢ですから、いつまで続くのかはわかりません。将来的には、私がさつまいもの栽培までしなければならなくなるかもしれませんね」。
●六兵衛おろしについて
「さつまいもの粉とすりおろした山芋をこね(お湯を少し入れることもある)て生地をつくり、『六兵衛おろし』で押し出して麺をつくります。『六兵衛おろし』の穴は、ブリキに釘で穴を開けたものです。ミンチをつくる機械で押し出すと表面がツルツルですが、釘で穴を開けたものだと、表面に凸凹ができます。これでツユが麺にうまくからむんです。ラーメンやうどんみたいに麺が長くなくて短いから、余計に表面にツユがからむ必要があるんですよ。押し出す作業は本当に大変ですが、毎日黙々とやっていますよ(笑)」。

『よしだや』の麺、麺の生地を使った『ろくべえまんじゅう』は、スーパーなどで販売されている。

また、吉田さんのお母様が島原市中心部の『一番街アーケード』の一角で直接販売。

「昔はね、雨降りの日は農作業ができないから、その時に『六兵衛』をつくっていたんですよ。『六兵衛』は便秘に効くみたいだし元気になるよ。私も80歳過ぎても元気だしね(笑)」と、吉田さんのお母様。
■よしだや
長崎県島原市門内町丙640-2
0957-64-1655
http://www.shimabara.jp/yoshidaya/
営業/9:00〜14:00
休み/日曜

![]()
さつまいもを干して粉にしたものとすりおろした山芋やお湯を合わせてこね、『六兵衛おろし』にのせて押し出し、蒸すかゆでる
昆布、カツオなどの出汁をベースに醤油で味付けする。麺に甘味があるので、やや濃い味付けにしている
温めたツユと麺を合わせて器に盛り、ネギやカマボコをのせてできあがり。柚子こしょうが添えられることが多い
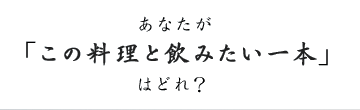
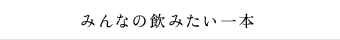



3本の中から飲みたい一本をお選びください。
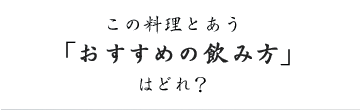
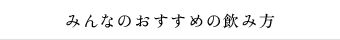



3種類の飲み方からおすすめを一つお選びください。